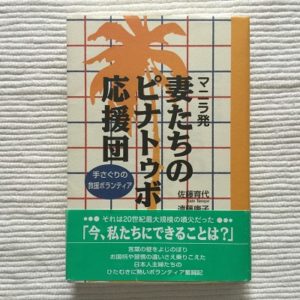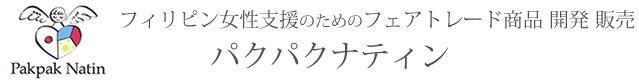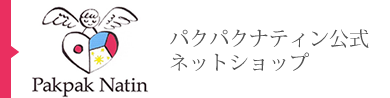- Home
- 「パクパクナティン」のフィリピン女性の支援活動
「パクパクナティン」のフィリピン女性の支援活動
パクパクナティンの活動 / Activity
●フィリピンの伝統織物・手工芸品の商品開発と輸入販売
フィリピンの女性職人が継承する伝統織物や手工芸品を輸入することで、彼女たちの伝統技術継承と収入向上を支援しています(フェアトレード)。商品づくりにおいては、作り手の暮らしと環境に配慮し、環境負荷の小さい自然素材や手仕事をいかした商品づくりをしています。活動を通して日本とフィリピンの市民が交流し、お互いの文化を知り、尊重し、理解を深めることをめざしています。
フィリピンの自然素材(アバカ麻、ラフィア、パイナップル布、ココナツほか)を活用しながら地域の環境を守り、伝統手工芸の継承を目指すパナイ島のNGOや、ルソン島イロコス地方の希少布ビナクルの復興プロジェクト支援(→エシカルブランド「HABI PRIDE」)をしています。人の手で動かす伝統の木製機織り機は、消費電力ゼロでエコロジカルです。
7100の島からなるフィリピンでは多彩な伝統織物が女性たちによって継承されていますが、職人の高齢化が進み、担い手不足が問題になっています。しかし追い風としてフィリピンは経済成長が続き、中間層も育ったことで伝統織物への関心も高まってきています。失われつつある伝統織物を復興しようと、NGOや政府が女性職人支援を始めています。私たちはこうしたNGOと交流しています。
●フィリピンの伝統文化や女性たちの手仕事に価値を
2019年から、ルソン島北部イロコス地方のビナクル織の復興と継承に取り組む女性職人の支援に力を入れています。日本とフィリピンの職人の協力で、エシカルバッグのブランド「HABI PRIDE」を立ち上げました(HABIとは、フィリピノ語で織物という意味)。日本ではほとんどフィリピンの伝統織物は知られていません。手仕事による上質なエシカルバッグの販売を通して、豊かな伝統織物文化を日本で紹介したいと考えています。
SDGsの達成目標は「2.つくる責任 つかう責任」「5.ジェンダー平等を実現しよう」「1.貧困をなくそう」です。

●フィリピン文化や日比のつながりを学び合うワークショップ、フェアトレード&エシカル消費の推進活動
市民勉強会などでワークショップを行っています。テーマは「バナナからフェアトレードを考える」「フィリピン料理」「リサイクルペーパービーズ」「アップサイクル」「フェアトレードとエシカル消費」ほか。
また、フェアトレードタウン世田谷推進委員会に参加しています。
人権と環境に配慮したフェアトレード&エシカル商品の販売を通して啓発活動をおこない、「エシカル消費」を推進し、共に生きる持続可能な社会をめざします。
★エシカル消費とは、環境や社会、人に対して配慮されてつくられたものを選んで消費することです。フェアトレードはエシカル消費のひとつです。
定例ミーティングを月に2回行っています。
★ご寄付は基本的には受け付けておりません。しかし、自然災害等が発生し、現地の支援が必要とされた場合、広く市民に寄付を募り、現地へ緊急援助を行っています。
●著作
*市民勉強会の成果を出版
『地球買いモノ白書』どこからどこへ研究会 コモンズ 2003年 本体1300円
身近な商品が生産者や環境にどんな影響を与えているか、市民の視点で世界中から情報を集めて検証。フェアトレードやエシカル消費について学ぶ入門書として最適です。
★書評 毎日新聞 2003.8.22.
日本の家庭にあふれる価格の安い輸入品。それらはどうやって生産されているのだろうか。そんな疑問を抱いたNPOのメンバーや主婦ら13人が「どこからどこへ研究会」をつくり、モノの由来を調べて、この本にまとめた。/ 焼き鳥のチキン、回転ずしのマグロ、カップ麺のエビ、缶コーヒー、携帯電話など九つのモノを取り上げている。それらがいかに安い労働力で成り立ち、いかに途上国の環境破壊につながっているかを数字やイラストなどでわかりやすく解説。焼き鳥用の鶏肉を加工するタイの工事用では10代の女性たちが朝から夜まで安い賃金で鶏肉をくしに刺し続ける。安ければそれでいいのかと問いかける。
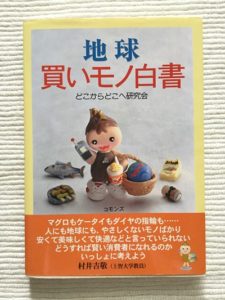
*災害救援の活動記録
『マニラ発 ピナトゥボ応援団』佐藤育代・遠藤康子著 明石書店 1999年 本体1600円
20世紀最大といわれたピナトゥボ火山大噴火災害を伝える救援ボランティアの記録です。
★朝日新聞 論説委員室から『窓』 「ピナトゥボの妻」 1999年4月24日
夫の赴任にあわせフィリピンで5年間を過ごした佐藤育代さんは帰国後、強い喪失感、疎外感にとらわれたという/マニラでは、3人の子どもや義父の世話をする傍ら、「ピナトゥボ救援の会」の会長として走り回った/8年前、今世紀最大級の噴火で多くの被害を出した山の周辺は、その後も雨期のたびに、火山灰が荒れ狂う泥流となって下流の町村を襲っている。/日本人駐在員の妻らが噴火直後にこの会を結成し、ふもとに住む少数民族アエタら、被災者を息長く支援してきた。/だが、帰国してしまえば、ボランティア経験を生かすどころか、友人に滞在中の話をすることさえはばかられる気がした。消費財のあふれる日本はあまりの別世界。話しても分かってもらえないだろう、自分は変わったのに日本は昔のまま……。/そんなもどかしさを、現地で一緒に活動した遠藤康子さんとともにワープロにぶつけて、600枚の活動記録にまとめた。/例えば、バナナの葉から紙をすく技術を被災女性らに伝え、便せん用に買い取るプロジェクト。子どもらへ給食、奨学金の援助。水牛の購入費を農民に融資する事業も軌道に乗せた。/実績が買われて、アジア開発銀行で事例研究の発表をし、マニラ首都圏の繁華街では写真展も開いた。/失敗談も含めて、手作りの活動ぶりが生き生きと描かれた記録は、編集者の目にとまり、「マニラ発 妻たちのピナトゥボ応援団」(明石書店)の題で出版された。/振り返ると、現地の人との交流の楽しさや、日本人と違う生き様に対する好奇心が行動の原動力になったという。「援助した」というよりむしろ、得るもののほうが多かったとも。/多くの主婦に引き継がれた会は来年、幕をおろす。<直>